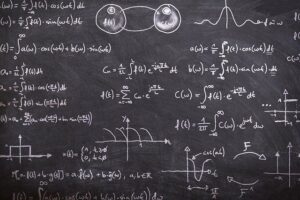自己啓発やビジネス書でも馴染み深くなってきた心理学の分野には、教科書にも引用される有名な実験が数多く存在している。
しかしながら、その中には誤解や誤解釈、ただの茶番劇になってしまった研究も多く存在する。
「現代の倫理観による再現性の難しさ」や「実験のインパクト」だけで生き残ってきた、ゾンビ研究らの代表である「ミルグラムの服従実験」・「キティジェノヴィーズ事件」・「窓割れ理論」について、その真実や実験の詳細、誤解が生じた原因について紹介していく。
心理学の分野において、正しい知識と理解が重要であることを再認識し、より深く掘り下げていく。
ミルグラムの服従実験

心理学において有名な実験者の1人に、スタンレーミルグラムがいる。
1961年6月18日、彼はニューヘブン・レジスター紙に全面広告を載せた。
「ご協力くださった方には、1時間につき4ドルをお支払します」。
それからの数か月間、何百人もの人が、イェール大学にあるミルグラムの研究室を訪れた。
被験者は2人1組になり、くじを引いて、1人は「先生」役、もう1人は「生徒」役になる。
先生は大きな装置の前に座るよう指示され、それは電気ショック発生器だと教わる。
その部屋には研究スタッフもいて、実験中に指示を出す。
一方、生徒は隣の部屋で椅子に縛られており、声だけが先生に聞こえるようになっている。
こうして記憶テストが始まるが、生徒が答えを間違えると、先生は研究スタッフの指示通りにスイッチを押して、生徒に電気ショックを与えなければならない。
実を言えば、生徒役はミルグラムの研究チームのメンバーで、しかも装置は少しも電気ショックを与えなかった。
しかし先生役は、それを知らなかった。
先生役の人は、この実験は記憶力に関する罰の効果を調べるものだと思っていたが、彼ら自身が実験の対象だったのだ。
電気ショックは15ボルトという弱い電圧から始まる。
そして生徒が間違えるたびに、灰色の実験着を着たスタッフが、電圧を上げるよう命じる。
15ボルトから30ポルトへ。
30ボルトから45ボルトへ。
隣室の生徒が苦痛のあまり金切り声をあげても、スイッチの表示が「危険」と書かれた域に達しても、電圧を上げ続ける。
350ボルトになると、生徒は壁を激しく叩き、それを超えると、隣室からは何も聞こえなくなった。
実験に先立ってミルグラムは、仲間の心理学者、40人ほどに被験者はどこまで電圧を上げるだろう、と尋ねた。
彼らは揃って、450ボルトまで上げるのはせいぜい1%~2%で、完全な精神異常者だけだと言った。
実験の結果は衝撃的だった。
被験者の65%が電圧を上げ続け、ついには最大となる450ボルトの電気ショックを生徒に与えた。
ごく普通の父親、仲間、夫の3分の1は、見知らぬ人を感電死させても構わないと思ったのである。
なぜだろうか?
そうするよう指示されたからだ。
若き心理学者ミルグラムは、たちまち有名人になった。
新聞とラジオとテレビのほぼすべてが、彼の実験を取り上げた。
ニューヨーク・タイムズ紙は、「被験者の65%が苦痛を与えよ、という命令に無批判に従う」という見出しを掲げた。
記事はこう語る。
何百万という人々をガス室に送ることができるのは、いったいどんな人間だろう。
ミルグラムの実験結果から判断すると答えは明らかだ。
わたしたち全員である。
ミルグラムはユダヤ人で、最初からこの研究を、ホロコーストの究極の説明として発表した。
ミルグラムの説明はより洗練され、より知的で、何よりも、より不安にさせられるものだった。
ミルグラムから見れば、要になっているのは権威だった。
「人間は命令に無批判に従う動物だ」と彼は言う。
ミルグラムの結論、それは「人間には生まれつき致命的な欠陥があり、そのせいで、子犬のように従順に振る舞い、きわめて恐ろしいことも平気でする」というものだ。
ところが実際は、ミルグラムの台本通りに動こうとしない被験者は、強いプレッシャーをかけられた。
実験助手を務めた灰色の実験着をまとった男、ジョン・ウィリアムズという名の生物学教師は、被験者に高い電圧のスイッチを押させるため、強制的に8回や9回も実行するように求めた。
ある46歳の女性と口論になったことさえあったのだ。
なぜなら彼女が電気ショック発生器のスイッチを切ったからだ。
彼は再びスイッチを入れ、実験を続けるよう命じた。
「録画の音声を聞けば誰でも、これは権威への服従についての実験というより、むしろいじめと強制についての研究だと思うだろう」と被験者は書いている。
さて重要な問いは被験者が「自分は本当に電気ショックを与えている」と思っていたかどうかだ。
実験後まもなくミルグラムは、「数名の例外を除けば、被験者はこの実験の仕組みを信じて疑わなかった」と書いている。
しかし、ミルグラムの資料を読むと、被験者が疑っていることを示唆する言葉が、いくつも見つかる。
そもそも実験設定の異常さを思うと、驚くようなことではない。
イェール大学のような名門校の科学者が見守る中、罪もない人が電気ショックで拷問されて、殺害されるという状況を、被験者が疑わなかったりするだろうか?
実験を終えたミルグラムは、被験者全員にアンケートへの回答を求めた。
質問の一つは、「この状況をどれだけ信じられると思いましたか?」というものだった。
生徒が本当に苦しんでいると思っていたのは、被験者の56%にすぎないことを知った。
ミルグラムの研究アシスタントの分析によると、電気ショックを本物と思った人の大半は、スイッチを押すのをやめていたのだ。
では、被験者のほぼ半数が、この設定を見せかけだと思っていたのなら、ミルグラムの研究のいったい何が真実として残るのだろう。
ミルグラムは表向きには、自分の発見は「人間の本性の深遠で不穏な真実」を明らかにしたと述べた。
だが裏では、彼自身も納得していなかった。
「こうした空騒ぎが、意義深い科学を示唆するのか、単によくできた芝居なのかは、まだ何とも言えない。わたしは後者を受け入れつつある」。
1962年6月に彼は日記にそう書いた。
そもそもミルグラムの服従実験が調べたのは、人が権威に服従するかどうかだったのか、ということだ。
彼が「実験助手」のために書いた台本では、反抗的な被験者には、4つの具体的な「刺激」を与えるよう指示している。
そして現代の心理学者たちは、4つ目の「刺激」は命令だ、と指摘している。
実際、ドキュメンタリーの映像を見るとウィリアムズがこの言葉(命令)を発したとたんに、どの被験者も動きを止めることがわかる。
つまり、この刺激(命令)は即座に、不服従を導くのだ。
このことは1961年の最初の実験でも真実だったし、それ以後に行われてきた再現実験でも真実だった。
さらに電気ショック発生器を用いた何百回というミルグラムの実験を入念に分析したところ、実験者が高圧的になるにつれて、被験者がいっそう服従しなくなることがわかった。
権威者が横柄な態度を取ると、被験者は嫌悪感を抱いたのだ。
それならミルグラムはなぜ、被験者にスイッチを押し続けさせることができたのだろう?
心理学者のハスラムとライヒャーは、ある興味深い説を考え出した。
「被験者は灰色の実験着をまとった実験者に服従したのではなく、彼の仕事に参加することした」というのだ。
ハスラムとライヒャーは、被験者の大半は、協力したいという思いから実験への参加を志願したこと注目する。
つまり被験者はウィリアムズ氏の研究を助けたかった。
これは、ミルグラムがこの実験を平凡なオフィスで行うと、イェール大学という高尚な環境で行った場合に比べて、協力の度合いが落ちた理由を説明する。
また、(「この実験はあなたが続けることを必要とします」のような)科学的な目的を示唆する「刺激」が効果的だった理由も説明する。
そして、被験者が心のないロボットのようにではなく、疑念を抱きながら行動した理由も。
被験者は、すべては科学のためと言い続ける実験助手と自分を同一視し、一方では、隣室の生徒の苦しみを無視できなかった。
次のスイッチに進んだとしても、「これ以上はできない」、「もうやめる」と繰り返し叫んだ。
ある被験者は後に、自分が実験をやり通せたのは、当時6歳の脳性まひの娘のためだった、と語った。
医学界がいつか治療法を見つけることを願ってのことだ。
「わたしに言えるのは人間を助けるためなら、わたしは何でも喜んでやるということだけだ」と彼は言った。
実験を終えた被験者にミルグラムが、あなたの貢献は科学に役立つだろう、と伝えるとその多くは安堵の表情を浮かべた。
「お役に立ててうれしいです」というのが典型的な答えだった。
「世の中のためになるのであれば、ぜひともこの実験を続けてください。この混乱した世界では、わずかでも善なるものが必要とされているのです」と言った人もいた。
心理学者のドンミクソンは、1970年代にミルグラムの実験を再現した時、同じ結論に達した。
後に彼はこう述べている。
「実のところ人々は、多大な苦しみが伴っても、どうにか善良でありたいと思っている。善良であろうとすることに人々は囚われている……」
十分強くプッシュしたり、しつこく突いたり、うまく誘ったり操作したりすると、多くの人に悪事を行わせることができる。
しかし、悪は心の深みに潜んでいるので、引き出すには、相当な労力が要る。
そして、ここが肝心なのだが、悪事を行わせるには、それを善行であるかのように偽装しなければならない。
地獄への道は、偽りの善意で舗装されているのだ。
皮肉なことに、スタンフォード監獄実験でも、善意が重要な役割を果たした。
学生看守のデーヴ・エシェルマンは、明確な指示がなかったら自分はあのような行動 をとらなかったのではないか、と語った。
また彼は自分のことを「心は科学者だ」と言った。 後には、「自分は建設的なことをしたと思う」と語っている。
「なぜなら、形はどうあれ、人間の本性を理解することに貢献したからだ」 。
この点に関しては、 監獄実験を思いつき、ジンバルドの助手を務めたデーヴィッド・ジャッフェも同じだ。
彼は、善良な看守たちに実験の崇高な目的を伝え、囚人に対して厳しい態 度をとることを勧めた。
またジャッフェは看守役の学生に、こう言って約束させた。
「この研究から、 改革を促す重要な提言が生まれることを期待しよう。それがぼくらの目的だ。 ぼくらがこんなことをしようとしているのは、なんて言えばいいか、そう、ぼくら全員がサディストだか らじゃないんだ」
それから長い年月を経て、心理学者たちは、ミルグラムの研究に関しても同じ結論に至った。
被験者は研究者の考えに同調したに過ぎなかった。
電気ショック実験は、命令への服従に関する実験ではなかった。
それが調べたのは同調性だった。
現代でも80人程度の規模で再現実験は行われているが、オリジナルの実験よりも被験者が少ない上に、ミルグラムの服従実験における大きな問題点「参加者が研究者に同調してしまう」という問題を回避できないといけない。
単純にボタンを押したか・押して無いかだけでは意味がない。オリジナルの実験でも多くの人がボタンを最後まで押したからだ。しかし、既に述べた通り、被験者は実験の内容をうっすらと理解してのことだった。この時点で、実験は意味をなさなくなっている。
キティ・ジェノヴィーズ事件

「キティ・ジェノヴィーズ事件」とは、1964年3月13日、キャサリン・スーザン・ジェノヴィーズは、ガールフレンドのメアリアンと暮らすアパートへ急いで戻る最中に殺害されたという事件である。
しかし当時のキティの殺人事件は、その年のニューヨーク市で起きた636件の殺人事件の一つにすぎなかった。
一つの命が失われ、一人の恋人が消えたが、街は動き続けた。ところが週間後、この話は新聞の紙面を飾り、後に歴史の本に収められることになる。
そうなったは、殺人者や被害者にではなく、見物していた38名の人々の方に理由があったからだ。
メディアの狂乱は1964年3月27日、復活祭直前の金曜日に始まった。
ニューヨークタイムズ紙の一面には「殺人を目撃した三七人は警察を呼ばなかった」の見出しが掲げられた。
数十名の人間が犯行の現場を目撃していながら、誰一人として警察に通報せず、結果として一人の女性が殺されてしまった。
このキティの死は大々的に報じられたのである。
当時のソ連の新聞「イズベスチヤ」では、この事件は資本主義の「ジャングルにおけるモラルの欠如」の証拠だと記した。
ブルックリン地区の牧師は、アメリカ社会は「イエスを十字架にかけた人々と同じくらい病んでいる」と語った。
あるコラムニストは自国民を「冷淡で、臆病で、不道徳な人間」だと責めた。
ジャーナリストや写真家やテレビクルーが、キティが暮らしていたキューガーデンに殺到した。
その誰もが信じられなかったほど、そこに暮らす人々は礼儀正しく立派で、きちんとしていた。
そんな彼らがどうして、あの恐ろしいほど完壁な無関心を貫くことができたのだ。
テレビの影響で鈍感になったのだ、と主張する人がいた。
なぜ誰もキティ・ジェノヴィーズを助けようとしなかったのか?
それは誰もが冷たく、他人に対して無関心だったからだ、と結論づけられた。
この事件に関心を示したビブ・ラタネとジョン・ダーリーは、緊急事態における傍観者の行動実験を試みた。
被験者は大学生で、閉めきった部屋に一人で座り、同年代の学生数人とインターコムで学生生活についておしゃべりするよう指示される。
だが実を言うと、他の学生はいない。被験者が聞いているのは、研究者たちが事前に録音した音声だ。
まもなく、誰かがうめき始める。「助けて!誰か、助けて。お願い、誰か、た……死にそうだ……」
次に何が起きただろう。この叫びを聞いたのは自分だけだと思った被験者は、廊下に駆け出した。
被験者の全員が、その人を助けようと駆け出した。
しかし、最初に、近くの部屋に他五人の学生がいると説明され、その5人も叫び声を聞いていると思い込んだ被験者では、6%か行動を起こさなかった。
これが傍観者効果だラタネとダーリーの発見は、社会心理学にとって最も重要な発見の一つになる。
以来20年にわたって、緊急事態に傍観者がとる行動に関する論文と著書が1000本以上出版され。
また彼らが出した結果は、キューガーデンでの例の38人の目撃者が動かなかった理由も説明した。
キティ・ジェノヴィーズは、叫び声で多くの隣人を目覚めさせたにもかかわらず死んだのではなく、多くの隣人を目覚めさせたせいで死んだのだ。
近隣に暮らすある女性が後に記者に語った言葉は、それを裏づける。
彼女の夫は警察に通報しようとしたが、彼女は夫を引き留めた、「通報の電話はもう30本以上、かかっているはず」だと言って。
キティは、もし人気のない路地で襲撃され、目撃者が一人しかいなかったら、助かっていたかもしれない。
こうした連鎖が、キティをますます有名にしていくことになる。
ところが後々の徹底的な調査に基づいて再現したところ、実際の現場では配役が大きく変わることが分かった。
その日の経過だ午前11時9分。
ぞっとするような悲鳴が、オースティン街の静寂を破った。
しかし、外は寒く多くの住人は窓を締め切っていた。
だが悲鳴を聞いて外を見た人もいたが、通りが暗かったのでほとんどの人は異変に気づかなかった。
数人が「よろめきながら歩道を歩く女性」のシルエットを見たが、酔っ払っているのだろうと思った。
実は珍しいことではない。なぜなら近く酒場があるのだからで、少なくとも2人の住人が、電話で警察に通報した。
その1人はマイケル、ホフマンの父親で、マイケルは後に警察官になった。もう一人は、近くのアパートに住むハッティグランドだ。事件から何年も後に、ハッティはこう語った。
「警察は、この件についてはすでに何本か電話があった」と言いました。
しかし警官は来なかった。実は最初の通報を聞いて、警察はそれを夫婦喧嘩だと思ったらしい。
すでに警察を引退したマイケル・ホフマンは、現場への到着が遅れたのはそのためだと考えている。覚えておいてほしい。
これは、夫から妻への暴力が軽視され、夫婦間のレイプが犯罪と見なされかった時代の出来事なのだ。
だが、38人の目撃者については、どうなのだろう。
この悪名高い数字は、歌や芝居から大ヒット映画やベストセラーまで、あらゆるものに登場するが、その起源は、この事件について刑事が尋問した人々のリストにさかのぼる。
リストに記された名前の大半は、目撃者でさえなかった。
せいぜい物音を聞いたくらいで、中には、気づかず、寝ていた人もいた。
二人だけは明らかに例外だった。
一人は同じアパートに暮らすジョゼフ・フィンクだ。
変わり者の孤独な男で、ユダヤ人を嫌悪しており、近所の子どもたちはヒトラーになぞらえて彼を「アドルフ」と呼んでいた。
フィンクは事件が起きた時には目を覚ましていて、キティへの最初の襲撃を目撃したが、何もしなかった。
キティを運命にまかせたもう一人の人物は、近所の住人、カール・ロスで、キティとメアリ・アンの友人だった。
ロスは階段のところで2度目の襲撃を目撃した(襲撃は3度ではなく、2度だった)。
しかし彼は、酔っぱらっていたせいもあり、パニックになって走り去った。
ロスは警察に、「巻き込まれたくなかった」と語ったが、彼は、世間に注目されたくなかったのだ。
それは自分がゲイであることが世間に知られるのを恐れたからだ1964年当時、同性愛は完全に違法と見なされていた。
警察も、ニューヨーク・タイムズのような大手の新聞も、同性愛に危険な病気という格印を押していたので、ロスはその両一方を恐れていた。
ゲイの男性は日常的に警察に虐待されており、新聞は同性愛を疫病であるかのように描写していたのだ。もちろんこうした事情があったとしても、ロスの怠慢の言い訳にはならない。
酔っ払ってて、怖がっていたとしても、ロスは友人を助けるために何かできたはずだ。実のところロスは友人に電話をかけた。友人は、すぐ警官を呼ぶよう促した。
しかし、ロスは自分のアパートから警察に電話をかけようとはせず、屋根越しにアパートの隣人を訪ねた。
隣人はロスの話を聞いて、隣に暮らす女性を起こしたその女性はソフィア・ファーラーという名前だ。
キティが階下で血を流して倒れていることを聞くと彼女は一瞬もためらうことなく部屋を飛び出した。
後ろでは夫がズボンをはきながら待ちなさい、と叫んでいた。ソフィアは、殺人者と鉢合わせするかもしれないと思ったが、階段を駆け下りた。
「わたしはキティを助けるために走りました。そうするのは当然だと思ったのです」と彼女は語った。
ソフィア階段に出るドアを開けると、キティはそこに横たわっていた。
暴漢の姿はなかった。
ソフィアが両腕で抱きかかえると、キティは彼女にもたれ、全身の緊張を解いた。
こうしてキャサリン・スーザン・ジェノヴィーズは亡くなった。
彼女は近所の人の腕に抱かれて逝ったのだ。
キティの弟ビルは、長い年月が過ぎた後に、この話を聞いてこう言った。
なぜソフィアは忘れられたのか?
なぜ、どの新聞も、彼女のことに触れなかったのだろう。真実を知るとかなり落胆させられる。
ソフィアの息子によると「当時、母は新聞社の女性に一部始終を話した」そうだ。
しかし翌日の記事には、ソフィアは巻き込まれることを望まなかった、と書かれていた。
ソフィアはその記事を読んで激怒し、「マスコミの人間とは、2度と口をきかない」と誓ったのはソフィアだけではない。
実のところ、キューガーデンに暮らしていた数十人は、自分たちのが報道機関によって歪められ、曲解され続けることに苦しめられ、多くは、その地域を去った。
ついでに少しだけ触れた「傍観者効果」についてだが、多くの教科書で教えられている。
しかし、2011年に発表されたメタ分析が緊急事態における傍観者の行動に新たな光を当てた。
メタ分析というのは、研究について の研究で、過去に行われた多くの研究を分析する。
このメタ分析は、ラタネとダーリーによる最初の実験(部屋に学生を入れた実験)を含め、過去50年間に行われた105件におよぶ、傍観者効果に関する重要な研究を分析した。
そしてこのメタ分析からは、2つの洞察がもたらされた。
1つ、傍観者効果は確かに存在する。
わたしたちは、時に間違った介入によって非難されることを恐れ、何もしようとしないことがある。そのために誰も行動を起こしていないのを見て、まずいことは起きていないと思い込む。
では、2つ目の洞察は?
もしも緊急事態が明らかに命に関わるものであり、互いと話せる状況にあれば(つまり、別々の部屋などで孤立しているのでなければ)、逆の効果が起きる。
論文の著者曰く、「傍観者の数が増えると、救助の可能性は、減るのではなく増える」のだ。
「窓割れ理論」は幻想

ジェームズ・Q・ウィルソン教授、聞き覚えのない名前かもしれないが、アメリカの刑事司法システムが今日のようになった経過を理解するには、避けて通れない人物だ。
マーティンソンが自らの命を絶った数年後、ジェームズ・ウィルソンはアメリカの歴史の進路を変えた。
ハーバード大学の政治学教授だったウィルソンは、生命倫理から薬物戦争、法治国家の未来からスキューバダイビングまで、あらゆることに持論を持っていた。
しかし、ウィルソンのライフワークの大半は犯罪に関するものだ。
そして、嫌いなことが1つあるとすれば、右の頬をぶった人に左の頬を向けることだった。
彼は、受刑者に親切な刑務所を嫌悪した。
「犯罪行動の「原因」の探究は時間の無駄だ」と彼は言った。
「厄介な若者の害について不平を言う自由主義者は論点がずれている。世の中には価値のない人間が存在し、彼らは閉じ込めておくに限る。さもなければ、処刑するまでだ」というのが彼の考えだった。
「現在の見識ある多くの指導者を、残酷、さらには野蛮などと攻撃することは、わたしたちの混乱を示す尺度である」とウィルソンは記している。
ジェラルド・フォード大統領も、ウィルソンの考えを「最も興味深く、有益だ」と評した。
主要な高官がウィルソンの哲学に味方した「犯罪に対する最高の救済策は犯罪者を片づけることだ。難しいことではない」と、ウィルソンは繰り返し訴えた。
1982年、ウィルソンはアトランティック誌への寄稿にこう記した。
「割れた窓をそのまま放置したら、じきに他の窓もすべて破壊されるだろう」。
道端に散らかるゴミ、路上の浮浪者、壁の落書き。
そうしたものは全て、殺人や暴力の前兆だ。
割れた窓が一枚でもあると、ここでは秩序が守られていない「もっとやっていい」というメッセージが犯罪者に送られる。
したがって、重罪と戦うのであれば、割れた窓を修理するところから始めなければならない。
1980年代半ば、ニューヨーク市の地下鉄は落書きだらけだった。
交通局は、何か手を打たなければならないと考え、ウィルソンの共著者であるジョージケリングをコンサルタントに雇った。
彼は大規模な浄化を推奨した。
少しでも落書きされた車両は、直ちに清掃に回され、落書きはきれいさっぱり消された。
地下鉄の責任者によると、「わたしたちは徹底的に浄化を行った」。
続いて第二段階が始まった。
ウィルソンとケリングの「割れ窓理論」は、違法行為だけではなく、違法行為を行う人々にも適用された。
物乞い、ごろつき、浮浪者を野放しにしている都市は自ら状況を悪化させているようなものだ、と彼らは主張した。
結局のところ、ウィルソンが2011年に記したように、「社会秩序は脆い」のである。
他の多くの科学者と違って、ウィルソンは、貧困や差別といった犯罪の構造的原因の調査にはほとんど関心がなかった。
そうではなく、重要な原因はただ1つ、「人間の本性」だと、彼は考えていたウィルソンはこう考えた。
「大抵の人は、犯罪は割に合うどうかという単純な損得勘定をしている。もし警察が寛容で、刑務所が過度に快適なら、より多くの人が犯罪者の道を選ぶだろう。犯罪率が上昇しているのなら、その解決策は同様に単純だ。より高い罰金、より長い刑期、より厳しい執行といった外発的動機づけによって正せばよいのだ」と。
そのように取り締まれば、必然的に犯罪の「コスト」は上がり、需要は減る。
このウィルソンの理論を実践したくてたまらない人がいた。
ウィリアム・ブラットンは1990年にニューヨーク市警察の交通部門のトップに任命された人物である。
彼はウィルソンの理論の熱烈な信奉者で、アトランティック誌に掲載された最初の割れ窓理論の記事のコピーを誰彼なく配っているのは有名な話だった。
しかし、ブラットンがしようとしていたのは、割れた窓の修繕だけではなかった。
ニューヨークの秩序を立て直したかったのだ。
それも、情け容赦なく。最初にその標的となったのは、地下鉄の無賃乗車だ。
取り締まりは強化され、1.25ドルの切符を提示できなかった人は鉄道警察に逮捕され、地下鉄のホームで衆人環視の中、手錠をかけられ、整列させられた。
逮捕者の数は以前の5倍になった。
この成功はブラットンの食欲を満たすどころか、さらにかきたてた。
1994年、彼はニューヨーク市警の本部長に昇進し、まもなくニューヨークの全市民がブラットンの哲学を味わうことになった。
当初、警官たちは規則や慣習に動きを妨害されたが、プラットンはそれらを一掃した。
今や、誰でも、ほんの些細な違反でも、逮捕される可能性が出てきた。
公の場で酒を飲んだ、マリファナを所持していた、警官に軽口を叩いた、というだけで。
奇跡的に、この新たな戦略はうまくいっているように見えた。犯罪率は急落した。
殺人率は1990年から2000年までの間に63%減少した。
- 強盗は「64%減少」
- 車泥棒は「71%減少」
割れ窓理論は、かつてはジャーナリストに嚇笑されたが、天才的な名案だった。
ウィルソンとケリングはアメリカで最も尊敬される犯罪学者になった。
ブラットン本部長はタイム誌の表紙を飾り、2011年にはロサンゼルス市警察のトップに任命され、2014年にはニューヨーク市警の本部長に再度任命された。
ウィルソンはブラットンを、「わが国の警察活動における最大の変化」の功績者と評した。
割れ窓理論がアトランティック誌に初めて掲載されてから、ほぼ40年が経った。ウィルソンとケリングの哲学はアメリカ合衆国のすみずみにまで浸透し、さらにはヨーロッパからオーストラリアにまで広まった。
この実験では、研究者は環境の良い地域に車を一週間放置した。
彼は待った。何も起きない。次に彼は、ハンマーを手に戻った。
そして車の窓を打ち砕くと、たちまち堰は切られた。
数時間もしないうちに、通行人がその車を破壊し始めたのだ。
その研究者の名は、フィリップ・ジンバルド
ジンバルドの車の実験は、どの科学誌にも発表されなかったが、割れ窓理論にインスピレーションを与えた。
しかし、ジンバルドの「スタンフォード監獄実験」と同様に、この理論は偽りであることが暴かれてきた。
たとえば、ブラットンとその熱烈な支持者による「革新的」な取り締まりは、ニューヨーク市の犯罪率の低下の原因ではなかった。
その低下は、取り締まりのはるか以前から始まっていて、他の都市でも同様だった。
サン・ディエゴのように、厳しい取り締まりをしなかった都市でも、犯罪率は低下していた。
2015年、割れ窓理論に関する30の研究をメタ分析したところ、ブラットンの攻撃的な逮捕戦略が、犯罪の削減に貢献したという証拠は皆無であることが判明した。
甲板を掃除してもタイタニック号を救えないのと同じで、交通違反切符をせっせと切っても、その地域が安全になるわけではなかった。
さらに悪いことにニューヨーク市で逮捕者が急増すると、警官の違法行為も急増した。
2014年までに、数千人が参加するデモ行進が、ニューヨークはもとより、ボストン、シカゴ、ワシントンを含む他の都市でも繰り広げられた。
そのスローガンは、「割れた窓、奪われた生命」だった。
↑2023年になっても上記の動画ように、ろくな文献調査もせずに【窓割れ理論】という誤った理論の基に、軽犯罪を無くす防犯対策を考える人間は絶えない。どれだけ前後の仮説や理論が正しくとも、足元がグラついているなら意味は無い。(この方は、統計学の一般書籍も販売している人物でもある)
また2018年の夏、ノルウェーとアメリカの経済学者からなる、あるチームが両国の刑務所における再犯率に着目した。
チームの計算によると、ハルデンやバストイといった刑務所の受刑者の再犯率が地域社会への奉仕や罰金を言い渡された犯罪者より約50%低かった。
それは、個々の有罪判決に対して、将来起きる犯罪が平均で11件減ることを意味した。
加えて、元受刑者の就業率は40%高い。
つまりノルウェーの刑務所に入ると、他の国の刑務所よりも人生の進路が確実に変わるのだ。
ノルウェーでの再犯率が世界で最も低いのは、偶然ではない。
対照的に、アメリカの刑務所システムがもたらす再犯率は、世界最高レベルだ。
アメリカでは、受刑者の60%が2年以内に刑務所に戻るが、ノルウェーではその数字は20%だ。
バストイではさらに低く、わずか16%で、その刑務所は、全世界で最高の矯正施設になっている。
しかしノルウェーの方法は、おそろしくコストがかかるのではないだろうか?
2018年の論文の最後で、経済学者たちはそのコストと利益を集計している。
彼らの計算によると、ノルウェーの受刑者の収容にかかる費用は、有罪判決1件あたり平均6万1515ドルで、アメリカのほぼ2倍だ。
しかし、これらの前科者がふたたび犯罪に走ることが少ないので、ノルウェーの法執行機関の出費は1人あたり7万1226ドル節約できる。
また、彼らの多くは働き口を見つけ、政府の支援を必要とせず、税金を支払うため、さらに平均で6万7086ドルの節約になる。
最後に重要なこととして、犯罪被害者の数が減ることの価値は計り知れない。
ニューヨーク市警も数字だけ見れば、目覚ましい成果だろう。ニューヨークの犯罪数は激減し、逮捕者数は激増した。
そしてブラットン本部長はニューヨークのヒーローだった。
しかし、現実は数千人もの無実の人々と何千万ドルという無駄な税金が使われ、本当に捕まえるべき重罪犯は自由に歩き回っていただけだった。
そういうわけで科学者は、アメリカ警察の統計は当てにならないと考えている。
コラム:サードウェイブ実験の問題点
1967年に高校の歴史教師ロン・ジョーンズによって実施されたサードウェイブ実験は、第二次世界大戦前にドイツ国民がどのようにしてナチス政権を受け入れることができたのかを説明することを目的として行われた。
多くの文献では、実験を以下のように説明している。
- 1日目
ジョーンズは、「サードウェイブ」での権威の象徴としてふるまい、自分のクラスにルールや規則を追加し、実験を始めた。生徒が発言する前にジョーンズの許可を得ることや、常に姿勢を正す、持ち物を制限する等の軽いルールだっため、反発は起きなかった。当初は1日の予定だったが、生徒が実験の続行を望み、2日目以降も続くことになった。 - 2日目
ジョーンズは、ヒトラーに似た敬礼をおこなうことをクラスの生徒に指示した。この日以降、生徒達はジョーンズの指示がなくても定めたルールを守り実行した。規律を決めることで生徒達が自分一人ではなく、グループに属しているのだという意識を強く持ち始めたからである(マインドコントロール)。さらに、時が進むにつれて新たに規則やルールを望む声が増え幾つもの規則が作られた。 - 3日目
この実験は、現代世界史の授業の一環だったが、新たにこの授業に参加する生徒が増え、最初の30人から43人にクラスが拡張された。すべての生徒に会員カードが発行され、非会員等の入場を停止するなどの特別な措置を施した。さらに、ジョーンズは生徒に新しい会員の育成方法を教え、その日の終わりには200人以上の参加者がいた。ジョーンズは、活動の他のメンバーが規則を遵守しなかったとき、一部の学生が彼に報告を開始したことに驚いた(内部告発の発芽)。 - 4日目
この時点で、この活動はジョーンズにはコントロールができなくなっていた。外部の活動では暴力事件や喧嘩が多発し、ジョーンズは罪の重さを感じ実験を止めなくてはと考えた。生徒たちは他の高校にまで活動が及ぶ程この活動にのめり込み、規律と忠誠心は際立っていた。ジョーンズは、この活動が社会運動の一部であると発言し、翌日「サードウェイブ」のリーダーを、金曜日の正午の集会で公に発表すると発表した。 - 5日目
ジョーンズは、最初はスクリーンに何も映像を映さなかったが、数分後に「君たちが信じたものの正体を見せよう」とのニュアンスの発言をおこない、生徒たちが理解不能だったはずのファシズムの象徴、ヒトラーとナチス党員の映像を映した。この結果、生徒たちは我に返り本当の姿に衝撃を受け、中には涙を流す者もいた。
さてここからが本題だが、1960年代の心理学実験は非常に有名なもの多い。
しかしその後、研究者が実験に意図的に介入を行い、結果を大きく歪ませてしまっていたことが発覚するケースも珍しくない。
さらに、この1950年~1980年代の実験の多くは、現代の倫理観的観点から実験再現ことが難しく、知名度と実験の内容だけが一人歩きをしているだけというケースも少なくない。
そして、このサードウェイブ実験も2020年にアガタ・マルシニアクが出した論文では、教師のロイ・ジョーンズが人は権威の影響を受けやすいという結果を導き出す為に、意図的な介入を行った可能性を指摘している。
また一部の学者たちからも、被験者たちに対して、自己規律を持ち、規則を守ることが重要だと強調したり、実験に従わない生徒に対して制裁を課すなどの行動が取られたと言及されたり、他にもサードウェイブ実験の結果が実際の歴史的証拠と整合するかどうかも疑問視されている。
実際の歴史的出来事(当時のドイツ国民とナチス・ドイツ政権)を過度に単純化し、1クラスで行った実験結果へ当てはめている点も指摘されている。
ちなみに類似した実験では、小学校教諭だったエリオット・ジェーンが行った実験がある。
クラスの子どもに茶色の目をしている子は「聡明で頭も優れている」と伝え、逆に青色の目をしている子は「いつもボーっとしていて、頭も悪い」と伝えた。
すると、時間が経つにつれて茶色の目をした子どもが青色の目をした子どもを見下すようになり、数学が得意な青色の目をした子どもは、数学の授業で間違える回数が跳ね上がったのである。
この実験を通してエリオットは差別意識がどのようにして発生するのかを調べたようだが、脚色の部分を取り除くと話が変わってきたのである。
実は、エリオット自身が積極的に実験へ介入を行い、例えば青色の目をした子どもだけ後ろの席に座らせたり休み時間を短くするなど、目に見えて差別意識が芽生えるように操作したのである。(つまり純粋な自然観察から得られた、結果ではない)
余談だが、エリオットの実験について仮に本人が介入を行わなかった場合、どのような結果になるのかと質問をされたが、最後までエリオット本人は回答ができなかった。
このように古い社会心理学の研究は、「実験の物珍しさ」と「現代での再現性の難しさ」を後ろ盾にゾンビのごとく生き続けているが、仮に再検証を実行された場合、どれだけの実験が有効性を保持し続けられるだろう?
参考文献
・Persons Needed for a Study of Memory” New Haven Register (18 June 1961).
・ Stanley Milgram, Obedience to Authority. An Experimental View (London, 2009), pp. 30-31.
・Stanley Milgram, ‘Behavioral Study of Obedience’, Journal of Abnormal and Social 3. Psychology, Vol. 67, Issue 4 (1963).
・Walter Sullivan, ‘Sixty-five Percent in Test Blindly Obey Order to Inflict Pain’, New York Times (26 October 1963).
・ Milgram, Obedience to Authority, p. 188.
・Milgram said this in an interview on the television programme Sixty Minutes on 9. 31 March 1979.
・Amos Elon, ‘Introduction’, in Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil (London, 2006).
・ Arendt, Eichmann in Jerusalem.
・Harold Takooshian, ‘How Stanley Milgram Taught about Obedience and Social Influence’, in Thomas Blass (ed.), Obedience to Authority (London, 1999), p. 10.
・ Gina Perry, Behind the Shock Machine. The Untold Story of the Notorious Milgram Psychology Experiments (New York, 2013), p. 5.
・ Gina Perry, The Shocking Truth of the Notorious Milgram Obedience Experiments’, Discover Magazine (2 October 2013).
・ Milgram, ‘Behavioral Study of Obedience’.
・ Perry, Behind the Shock Machine (2012), p. 164.
・Gina Perry et al., Credibility and Incredulity in Milgram’s Obedience Experiments: A Reanalysis of an Unpublished Test’, Social Psychology Quarterly (22 August 2019).
・ Stanley Milgram, ‘Evaluation of Obedience Research: Science or Art?’ Stanley Milgram Papers (Box 46, le 16). Unpublished manuscript (1962).
・ Stephen D. Reicher, S. Alexander Haslam and Arthur Miller, What Makes a Person a Perpetrator? The Intellectual, Moral, and Methodological Arguments for Revisiting Milgram’s Research on the Influence of Authority’, Journal of Social Issues, Vol. 70, Issue 3 (2014).
・ Perry, Behind the Shock Machine, p. 93.
・ Cari Romm, ‘Rethinking One of Psychology’s Most Infamous Experiments’, The Atlantic (29 January 2015).
・ Stephen Gibson, ‘Milgram’s Obedience Experiments: a Rhetorical Analysis’,British Journal of Social Psychology, Vol. 52, Issue 2 (2011).
・Mere Authority: Evidence that in an Experimental Analogue of the Milgr Paradigm Participants are Motivated not by Orders but by Appeals to Science Journal of Social Issues, Vol. 70, Issue 3 (2014).
・ Perry, Behind the Shock Machine, p. 176.
・ S. Alexander Haslam and Stephen D. Reicher, ‘Contesting the “Nature” of Conformity: What Milgram and Zimbardo’s Studies Really Show’. PLOS Biology, Vol. 10, Issue 11 (2012).
・ Perry, Behind the Shock Machine, p. 70.
・ Blum, ‘The Lifespan of a Lie ‘.
・’Tape E’ (no date), Stanford Prison Archives, No.: ST-b02- f21, p. 6.
・ Perry, Behind the Shock Machine, p. 240.
・ Arendt, Eichmann in Jerusalem, p. 276.
・ Bettina Stangneth, Eichmann Before Jerusalem: The Unexamined Life of a Mass Murderer (London, 2014).
・’The Adolph Eichmann Trial 1961’, in Great World Trials (Detroit, 1997), pp. 332–7.
・ Ian Kershaw, “Working Towards the Führer.” Reflections on the Nature the Hitler Dictatorship’, Contemporary European History, Vol. 2, Issue 2 (1993).
・ Christopher R. Browning, ‘How Ordinary Germans Did It’, New York Review of Books (20 June 2013).
・ Roger Berkowitz, ‘Misreading ‘Eichmann in Jerusalem, New York Times (7 July 2013).
・Ada Ushpiz, “The Grossly Misunderstood “Banality of Evil” Theory’, Haaretz October 2016)
・Perry, Behind the Shock Machine, p. 72.
・ Matthew M. Hollander, The Repertoire of Resistance: Non- Compliance wit Directives in Milgram’s “Obedience” experiments’, British Journal of Sociat Psychology, Vol. 54, Issue 3 (2015). 40 Matthew Hollander, ‘How to Be a Hero: Insight From the Milgram Experiment Huffington Post (27 February 2015).
・Bo Lidegaard, Countrymen: The Untold Story of How Denmark’s Jews Escaped the Nazis, of the Courage of Their Fellow Danes- and of the Extraordinary Role of the SS (New York, 2013), p. 71.
・Peter Longerich, ‘Policy of Destruction. Nazi Anti-Jewish Policy and the Genesis of the “Final Solution” ‘, United States Holocaust Memorial Museum, Joseph and Rebecca Meyerhoff Annual Lecture (22 April 1999), p. 5. Lidegaard, Countrymen, 198.
・Martin Gansberg, ’37 Who Saw Murder Didn’t Call the Police’, New York Times (27 March 1964).
・Nicholas Lemann, ‘A Call for Help’, The New Yorker (10 March 2014).
・ Gansberg, ’37 Who Saw Murder Didn’t Call the Police’, New York Times. 4. Peter C. Baker, ‘Missing the Story’, The Nation (8 April 2014).
・ Kevin Cook, Kitty Genovese. The Murder, The Bystanders, The Crime That Changed America (New York, 2014), p. 100.
・Abe Rosenthal, ‘Study of the Sickness Called Apathy’, New York Times (3 May 1964). Gladwell, The Tipping Point, p. 27.
・Bill Keller, ‘The Sunshine Warrior’, New York Times (22 September 2002).
・ John M. Darley and Bibb Latané, ‘Bystander Intervention in Emergencies’, Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 8, Issue 4 (1968).
・Maureen Dowd, ’20 Years After the Murder of Kitty Genovese, the Question Remains: Why?’, New York Times (12 March 1984).
・Cook, Kitty Genovese, p. 161.
・Rachel Manning, Mark Levine and Alan Collins, The Kitty Genovese Murder and die Social Psychology of Helping. The Parable of the 38 Witnesses’, AmericanPaychologist, Vol. 62, Issue 6 (2007).
・ Mannen die moeder en kind uit water redden: “Elke Fitte A’dammer zou dit doen”, at5.nl (10 February 2016).
・ Vier helden redden moeder en kind uit zinkende auto’, nos.nl (10 February 2016),
・ Peter Fischer et al., ‘The bystander-effect: a meta-analytic review on bystander intervention in dangerous and non-dangerou8 emergencies’, Psychological Bulletin, Vol. 137, Issue 4 (2011),
・ R. Philpot et al., ‘Would I be helped? Cross-National CCTV Shows that Intervention is the Norm in Public Conflicts’, American Psychologist (June 2019).
・Cook, Kitty Genovese; Catherine Pelonero, Kitty Genovese. A True Account of a Public Murder and Its Private Consequences (New York, 2014); and Marcia M. Gallo, ‘No One Helped.’ Kitty Genovese, New York City, and the Myth of Urban Apathy (Ithaca, 2015).
・Baker, ‘Missing the Story.
・ Robert C. Doty, ‘Growth of Overt Homosexuality In City Provokes Wide Concern’, New York Times (17 December 1963).
・Pelonero, Kitty Genovese, p. 18.
・ Saul M. Kassin, ‘The Killing of Kitty Genovese: What Else Does This Case Tell Us?’ Perspectives on Psychological Science, Vol. 12, Issue 3 (2017).
・Ryan Berger, ‘Kriminalomsorgen: A Look at the World’s Most Humane Prison System in Norway’, SSRN (11 December 2016).
・Baz Dreizinger, ‘Norway Proves That Treating Prison Inmates As Human Beings Actually Works’, Huffington Post (8 March 2016).
・’About the Norwegian Correctional Service’, www. kriminalomsorgen.no (visited 17 December 2018).
・Dreizinger, ‘Norway Proves That Treating Prison Inmates As Human Beings Actually Works’.
・Manudeep Bhuller et al., ‘Incarceration, Recidivism, and Employment’, Institute of Labor Economics (June 2018).
・Berger ‘Kriminalomsorgen: A Look at the World’s Most Humane Prison System in Norway’, p. 20.
・Erwin James, ‘Bastoy: the Norwegian Prison That Works’, Guardian (4 September 2013). Genevieve Blatt et al., The Challenge of Crime in a Free Society, President’s Commission on Law Enforcement and Administration of Justice (1967), p. 159.
・Jessica Benko, ‘The Radical Humaneness of Norway’s Halden Prison’, New York Times (29 March 2015).
・Robert Martinson, ‘What Works? Questions and Answers about Prison Reform’, The Public Interest (Spring 1974).
・Michelle Brown, The Culture of Punishment: Prison, Society, and Spectacle (New York, 2009), p. 171.
・Robert Martinson, ‘New Findings, New Views: A Note of Caution Regarding Sentencing Reform’, Hofstra Law Review, Vol. 7, Issue 2 (1979).
・Adam Humphreys, ‘Robert Martinson and the Tragedy of the American Prison’, Ribbonfarm (15 December 2016).
・ Jerome G. Miller, “The Debate on Rehabilitating Criminals: Is It True that Nothing Works?’ Washington Post (March 1989).
・Risights, Like Those on Cutting Crime, That Tend To Prove Out’, New York Times (22 August 1998).
・ Richard Bernstein, ‘A Thịnker Attuned to Thinking; James Q. Wilson Has18 James Q. Wilson Obituary’, The Economist (10 March 2012)
・ James Q. Wilson, Thinking About Crime (New York, 1975), pp. 172-3
・Intellectual History’, American Affairs, Vol. II, Issue 3 (2018), 1982). 22 Gladwell, The Tipping Point, p. 141.
・Holman W. Jenkins, Jr, ‘The Man Who Defined Deviancy Up’, The Wall Street Journal (12 March 2011).
・James Q. Wilson, Lock ‘Em Up and Other Thoughts on Crime’, New York Times (9 March 1975). 27 Gladwell, The Tipping Point, p. 145.
・’New York Crime Rates 1960–2016′, disastercenter.com.
・Donna Ladd, ‘Inside William Bratton’s NYPD: Broken Windows Policing is Here to Stay’, Guardian (8 June 2015).
・ Jeremy Rozansky and Josh Lerner, ‘The Political Science of James Q. Wilson’, The New Atlantis (Spring 2012).
・Rutger Bregman, Met de kennis van toen. Actuele problemen in het licht van de geschiedenis (Amsterdam, 2012), pp. 238–45.
・Anthony A. Braga, Brandon C. Welsh and Cory Schnell, ‘Can Policing Disorder Reduce Crime? A Systematic Review and Meta- Analysis’, Journal of Research in Crime and Delinquency, Vol. 52, Issue 4 (2015).
・John Eterno and Eli Silverman, ‘Enough Broken Windows Policing. We Need a Community-Oriented Approach’, Guardian (29 June 2015),
・ P. J. Vogt, ‘#127 The Crime Machine’, Reply All (podcast by Gimlet Media, 12 October 2018).
・Dara Lind, ‘Why You Shouldn’t Take Any Crime Stats Seriously’, Vox (24 August 2014). AFEZKOLE, Liberty Vittert, ‘Why the US Needs Better Crime Reporting Statistics’, The Conversation (12 October 2018).
・ Michelle Chen, ‘Want to See How Biased Broken Windows Policing Is? Spend a Day in Court’, The Nation (17 May 2018). E ɔt t Y-(Hi kt C ESt, DAF . Robert J. Sampson and Stephen W. Raudenbush, ‘Seeing Disorder: Neighborhood Stigma and the SocialConstruction of “Broken Windows” ‘, Social Psychology Quarterly, Vol. 67, Issue 4 (2004). KLV ER TE5)YI, – ÆD The Atlantic e
・ Braga, Welsh, and Schnell, ‘Can Policing Disorder Reduce Crime? A Systematic Review and Meta-Analysis’.
・ Sarah Childress, ‘The Problem with ““Broken Windows” Policing’, Frontline (28 June 2016).
・ Vlad Tarko, Elinor Ostrom. An Intellectual Biography (Lanham, 2017), pp. 32-40. ・Arthur Jones and Robin Wiseman, ‘Community Policing in Europe. An Overview of Practices in Six Leading Countries’, Los Angeles Community Policing (lacp. org).
・Sara Miller Llana, ‘Why Police Don’t Pull Guns in Many Countries’, Christian Science Monitor (28 June 2015).
・Childress, The Problem with “Broken Windows” Policing’.
・ Beatrice de Graaf, Theater van de angst. De strijd tegen terrorisme in Nederland, Duitsland, Italië en Amerika (Amsterdam, 2010).
・ Quirine Eijkman, ‘Interview met Beatrice de Graaf over haar boek’, Leiden University (25 January 2010).
・ Joyce Roodnat, “Het moest wel leuk blijven””, NRC Handelsblad (6 April 2006).
・ Jon Henley, ‘How Do You Deradicalise Returning Isis Fighters?’, Guardian (12 November 2014).
・Hanna Rosin, ‘How A Danish Town Helped Young Muslims Turn Away From ISIS’, NPR Invisibilia (15 July 2016).
・Richard Orange, “Answer hatred with love”: how Norway tried to cope with the horror of Anders Breivik’, Guardian (15 April 2012).
・Prison Policy Initiative, ‘North Dakota Profile (prisonpolicy.org, visited 17 December 2018).
・ Dylan Matthews and Byrd Pinkerton, ‘How to Make Prisons More Humane’, Vox (podcast, 17 October 2018).
・Dashka Slater, ‘North Dakota’s Norway Experiment’, Mother Jones (July/August 2017).
・ National Research Council, The Growth of Incarceration in the United States. Exploring Causes and Consequences (Washington DC, 2014), p. 33. 35 Francis T. Cullen, Cheryl Lero Jonson and Daniel S. Nagin, ‘Prisons Do Reduce Recidivism. The High Cost of Ignoring Science ‘, The Prison Journal, Vol. 91, Issue 3 (2011).
・M. Keith Chen and Jesse M. Shapiro, ‘DoHarsher Prison Conditions Reduce Recidivism? A Discontinuity-based Approach American Lauw and Economics Review, Vol. 9, Issue 1 (2007).
・ “Louis Theroux Goes to the Miami Mega-Jail’, BBC News (20 May 2011).
・ Berger, ‘Kriminalomsorgen: A Look at the World’s Most Humane Prison System in Norway’, p. 23.
・ Slater, ‘North Dakota’s Norway Experiment’.
・ Cheryl Corley, ‘North Dakota Prison Officials. Think Outside The Box To Revamp Solitary Confinement’, NPR (31 July 2018).
・Slater, ‘North Dakota’s Norway Experiment’.
・Peter Fischer et al., ‘The bystander- effect: a meta- analytic review on bystander intervention in dangerous and non- dangerous emergencies’, Psychological Bulletin, Vol. 137, Issue 4 (2011).
・A. Marciniak et al. “Epiphanic “The Third Wave Experience” – Ron Jones and students.” Studia z Teorii Wychowania (2020). https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.1975.
・Stephen G. Bloom, ‘Lesson of a Lifetime’, Smithsonian Magazine (September 2005).